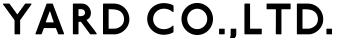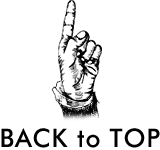2020.08.25
<映画:殺人の追憶 #ポン・ジュノ監督 #緊張と緩和 #終わりのないサスペンス映画 #混乱と余韻 >
こんばんは。
No Cinema, No Life.
火曜日担当のツノムラです。
映画は一日に二本までと決めています。
なぜなら、観終わって頭が混乱したままで、その日の残りの生活が、直近のまだ生暖かい映画の余韻に影響されて、何かしくじりそうな心配があるからです。
例えば、殺人事件の映画を二本連続で見た後に用事で外出するとします。
映画のせいで暴漢が心配になって、護身用に折り畳み式ナイフを鞄のポーチに忍ばせそうになる。しかし、流石にこれはマズイと正気に戻り、そのナイフを家に置いて外に出かける。
もし、三本以上連続で殺人事件映画を見ていたら、自己防衛本能のリミッターが振り切れそうになる。
街角で何度も後ろを振り返り、ポケットの中の拳は、握りしめている。
肩で風を切る勢いで後ろを凄む。殺人犯が後ろから迫ってこないか。
「殺られるか、やられるか」
「Dead or Alive」
すいません。妄想で取り乱しました。頭は正常です。
しかし、映画への感情移入は、誰しもありますよね。
本日は、心がザワつく「混乱」と「余韻」の大御所である、ポン・ジュノ監督の作品をご案内します。
『パラサイト/半地下の家族』、『グエムル』、『スノーピアサー』、『ほえる犬は噛まない』、どの作品も上映中は身動きがとれないほどに無我夢中に没入する。
ポン・ジュノ監督の才能を形容する言葉は多々ある。
<無駄を削いだテンポの速いスリルとサスペンス>
<絵画的でスケールが大きいカット割りと舞台美術>
<役者の癖のある顔芸と細かすぎるディテール演出>
そして、世界最高峰のエンターテインメント映画監督であることは間違いない。
しかし、いつも、映画作品の結末はアレなんです。
最後は宙ぶらりんのまま、心がザワついたまま劇場を後にすることになる。
「何故にそんな終わり方をする?」
「それで良かったのかい?」
スッキリしない居心地の悪い感情が残存し、頭は当分、その事ばかり考えている。
そして、数日後に突然に腑に落ちる。
信号待ちでぼおーっとしていると
「あれは、そういう事だったのかも知れない」
「あれは、あれで仕方がない事なんだ」
宙ぶらりんのままの映画のパズルの空白が時間差ではまる時がある。
映画の快楽が遅れて押し寄せる。
駄目だ。ポン・ジュノ製ドーパミンの中毒になりそうだ。
ご案内する『殺人の追憶(2003年公開、ソン・ガンホ主演、130分←少し長いけど大丈夫)』は、とてもスピード感があるサスペンス映画ですが、後をひきます。
映画の概要をほんの少しだけ失礼します。
韓国の軍事政権下の1980年代、ソウル南部の長閑な農村地帯である華城市で10人の犠牲者を出した連続強姦殺人事件が起きた。
韓国内を震撼させる猟奇的殺人事件であり、延べ167万人の警察・機動隊を動員した大捜査が行われた。しかし、未解決のまま2006年に公訴時効が成立した。
本作は、この実際に起こった事件をベースに脚本化された。
物語のはじまりは、用水路から後ろ手を縛られた女性の遺体が発見される。
地元警察が捜査にあたるが、捜査は進展しない。
雨の日に限って事件は連続して起きる。
そして、犯人は大胆にも殺人予告らしきメッセージを残す。
ソウル市警から若手エリートのソ刑事が加わって、徐々に犯人像に迫って行く。
大まかには、こんなストーリーです。
続きは是非に本作をご覧ください。
(若い女性の猟奇的殺人事件でショッキングなシーンもあるので、誰にもお勧めできるわけではありません)
僕が気になるのは
1:「地元警察のパク刑事(ソン・ガンホ)の顔芸」
→「また、やられた」のあきらめの顔
2:「取調室でのチョ警部(キム・レハ)の飛び蹴り」
→ビーバップ・ハイスクルーを超える鮮やかな不良喧嘩殺法
3:「ク刑事課長(ピョン・ヒボン)の変顔」
→とにかく印象深い顔で、ポン・ジュノ映画の田中邦衛みたいな役割
息が詰まるシリアスな場面に、この3人の刑事、いわゆるスリー・アミーゴスのユーモラスな変顔と動きを掘り込んでくる。
ポン・ジュノ監督の「緊張と緩和」は好きです。
本作は、時効前の2003年公開当時には韓国内で500万人を動員した。
日本でも、2000年から始まった「シュリ」、「JSA」、「冬のソナタ」の一連の韓流ムーブメントの流れで、大ヒットしました。
ポン・ジュノ監督は、当時34歳で本作が長編2作目でしたが、今村昌平や黒澤明の再来かと思うほどに強い衝撃を受けたことを覚えています。
そして、2020年には、「パラサイト」でパルム・ドール(最高作品)とアカデミー・オスカー(脚本、監督、作品の三冠)を受賞して、世界の映画ファンが愛して、尊敬してやまない映画監督になりました。
「パラサイト」のインタビューで、監督は自身のオリジナリティについて、答えている。
"映画表現がいつも肉体的であることを望んでいる"
"社会的である前に、変態的である自身のアイデンティティから離れないようにして、人間を掘り下げている"
監督は、『肉体的』と『変態的』に真正面から向き合っている。
僕は激しく同意し、感激しました。
この二つの魔性はとても個人的な事で、恥ずかしくて人には言えない。
普段は理知的に隠している(家族にも内緒で)。
例えば、監督が日本で撮影した「シェイキング東京」では、主人公(香川照之)が使い終わったトイレロールの芯を内股にぐりぐりとめり込む。
青あざが残るまで、ニヤニヤしながらぐりぐり。
しばらくして、夕方に内股の丸い正円のアザのある無しを確かめる。
映画に関係のない、こんな描写を、監督は突然に掘り込む。
この場合、アザは肉体的な映画表現であり、再確認の行為は変態である。
トイレロールの芯遊びについて、実は僕も幼少の頃に同じ体験がある。
でも、忘れていた。映画でその体験を思い出し、居心地が悪くなった。
懐かしいのではなく、恥ずかしくなった。
ポン・ジュノ作品は、自分でも忘れていた傷後と痛み、場所と臭い、湿度と金属音の軋みだとかを引きだす。
うまく言えないけれど、肉体を通してへばり付いた心のヒダが、独特の映画表現を通じて呼び覚まされる。
それも、フェチ、恥ずかしい癖みたいな、変態的な映像表現で胸の奥底をくすぐる。
「パラサイト」のあの屋敷での、地下室とフェチ、雨とニオイ。
あーもう。最高の映画でした。
是非、新作「パラサイト」もご覧ください。
それでは、おやすみなさい。