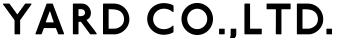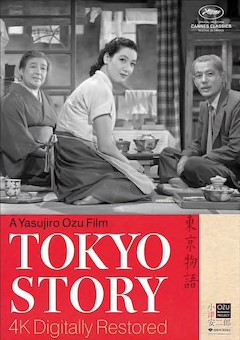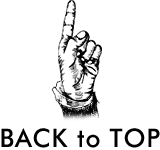2020.10.20
<映画:東京物語> #小津安二郎監督 #笠智衆と原節子 #ロー・アングル撮影(小津調) #あと味とものの哀れ
こんばんは。
No Cinema, No Life.
火曜日担当のツノムラです。
唐突ですが、今日は小津映画です。
小津安二郎監督の作品を観る。
そして、その映画世界を考えることは難しく、苦痛である。
反面、とても喜ばしいことでもある。 と言われている。
映画好きの大人から勧められて、20代の頃に『浮草』、『秋刀魚の味』、『麦秋』、『東京物語』など一通りの小津作品を観たものの、退屈であった。
「映像の様式美が優れていると言えばそれまでだが、話の本質について考えると何も理解できず、頭の芯が痛くなる」
そのように感想を述べると、周囲のインテリの大人達はニンマリと応える。
「君は小津映画を理解しつつある」
「小津安二郎は映画でテーゼ(命題)を何も語らない」
「だから、あと味が残るのだよ」
と上機嫌に褒める。
「僕が理解しつつある」だって?
「こっちは、全く意味が分かっていないのに」
それは全くの禅問答の世界である。
以来、小津映画作品は小難しいと敬遠してきました。
しかし、先日に無印良品店でMUJI BOOKSシリーズの『小津安二郎』を手にとって読み、俄然と興味が湧いてきた。
小津さんのエッセイは、気さくで楽しい。
助監督時代のほろ苦い思い出、通勤電車で乗り合わせる人物描写、ご自身の生涯独身生活と母との二人暮らしのこと、俳優の性格と表情、ローアングル撮影との出会いなど、好き嫌いがハッキリしている小津さんは、サバサバとユーモアたっぷりで語っている。
『小津安二郎はとても面白いおじさんだ!』
大監督に対して失礼な物言いですが、気難しいお人だと思っていたのに、読むに従ってとても身近に感じてくる。
本文の最後に、監督が描いた絵コンテも交えながら「映画の文法」について彼自身の言葉で丁寧に解説している。
感情をより細かく、また強く表現するためのクローズ・アップ(大写し)、時間経過を示すフェード・アウト(溶暗)とフェード・イン(溶明)など、従来のカメラワークを極力に省略する。
場面の変化も、舞台セットが変わるものの、前後シーンと同じ構図で、固定したローアングルから縦に奥深く被写体を捉える。そして、計算され尽くしたカットを暗転なしにつなぐ。
不必要な説明をすべて省略し、これまでの映画的文法を無視して、映画を撮る。
研ぎ澄まして、混じり気をなくし、純化した表現に修練される。
しかし、その省略は、観客を置き去りにはしない。
僕たちは、腹が七分目の感じで、頭の中に喜怒哀楽が満たされている。
19歳で松竹映画に入社し、監督助手の下積み時代が長かった小津さんは、当然に映画理論を熟知している。そして、最後にこう書いている。
“私は、理論を重んじる事も、軽んじる事も嫌いだ。天邪鬼かもしれないが、物事の判断を好きか嫌いかで決めるだけである”
“映画ってのは、あと味の勝負だと僕は思っていますよ”
130分間の映画表現で全てが完結しない、『あと味の大事』。
僕たちが生業にしている洋服もそうありたい。
小津さんが語る日本的な「ものの哀れ」について、僕も40代後半になってようやく少しは理解できるようになりました。
さて、前置きが長くなりましたが、本日は小津作品の中で、多分に皆が一番大好きな『東京物語』をご案内します。
1953年公開のモノクロ作品で、笠智衆と東山千栄子が演じる老父婦が東京に暮らす子供たちの家族に会いに行き、また尾道の住いに戻るというロードムービーです。
舞台は1953年、瀬戸内を望む長閑な「尾道」と戦後復興と毎日の忙しさに埋没する「東京」の家族。
平山周吉(笠智衆)は、市役所の務めを定年退職し、今は隠居しており、妻の「とみ(東山千栄子)」、末娘で教員の「京子(香川京子)」と三人で尾道の高台に暮らす。
他の子供達は、早くに独立し、尾道を離れて東京や大阪に暮らす。
長男の幸一(山村聰)は、内科の開業医で二児の父親。長女の志げ(杉村春子)は美容室を経営し、何人かの弟子を抱えている。
次男の昌二は戦死し、その妻で未亡人の紀子(原節子)が一人慎ましく暮らすことに、周吉は気掛かりでいる。
周吉の旧友やご近所からは、自立した立派なご子息に恵まれたことを羨まれる。
周吉は「そうではありません」と謙遜するが、本心はどうかわからない。
そんな折に、周吉ととみの老夫婦の二人きりで東京で暮らす3つの家族に会い行く。
急行列車で15時間の長旅である。70歳近い年寄りには体にきつい。
東京行きを子供たちから誘った素ぶりはない(ここの説明も映画では省略されている)。
両親が東京に着くや、長男と長女が「いつまで東京に滞在するのか? その間に誰が面倒をみるのか?」を思案している。
取り急ぎ、義理の妹で未亡人の紀子に両親の東京見物(はとバス)をお供するように取りまとめ、押し付ける。
そして、挙げ句の果てに子供達で金を工面し合い、老夫婦を熱海の温泉旅館に送り出す。彼らは日々の生活が忙しく、両親にかまう余裕がないと主張する。
周吉は、望まない熱海旅行をあてがわれるが、不平不満を言わない。
「ありがと、ありがと」と尾道の言葉で頭を下げる。
そして、年老いた二人は、東京の街をさまよい、迷い、熱海の喧騒に戸惑う。
「東京物語」とは、二人の目線からの東京を物見遊山するというよりも、東京という無機質の事物からを視点に、戸惑う老夫婦を遠目に眺めている。
そんなカメラ・アングルに観客は東京という無味で三人称的な視点を受け持つ。
そして、こう思う。
「年老いた両親が遠く離れた東京の家族に会いにきたのに、その態度と仕打ちは一体全体に何なのか?」
僕は頭にくる。
実の息子と娘なのに、全てを金で解決しようとするように見える。
自分の生活の忙しさを盾にして。
余りにも薄情である。
戦後8年しか経ていない。
戦前の家族制度の瓦解と喪失のスピードが早すぎる。
さらに、子供たちは生まれ育った尾道の言葉を使わずに、東京弁の早口で両親をまくし立てる。
そこまでに薄情さがエスカレートする訳を知りたい。
この件について、映画の残り50分で小津監督は舞台を尾道に移して、紀子(原節子)と周吉(笠智衆)の会話の中で、「変わること」と「忘れること」について「家族の幻想」を伝えようとしている。
とても間接的でいて、普遍的な語らいで「家族とは」を伝えようとしている。
いわゆる、『あと味』の余韻をもってして、「家族」を考えさせられる。
この続きは、是非とも本作をご覧ください。
Amazonプライムにて動画配信しています。
最後に、僕が気になるポイントです。
<1.世界が敬愛する小津映画>
本作は、10年毎に英国映画協会が主催する「2012年:世界の映画監督が選ぶ映画50選」で第一位に選ばれています。
日本人がノーベル賞を受賞したのと同じくらい嬉しい快挙です。
ちなみに、2位はキューブリック監督の「2001年宇宙の旅」とオーソンウェールズ監督の「市民ケーン」が同順位です。
外国からのからのお客様、とりわけ家族主義が強いカトリック系ヨーロッパやペルシャ、アラブ系の方々と話す機会があると、日本人の視点からの『東京物語』の解釈について尋ねられることがあります。
そんな時は、映画監督:吉田喜重さんの著書「小津安二郎の反映画」に書かれている解釈を引用します。
“小津映画について語ることは「両手で水をすくう」ことと同じだ。
すくえたと思っても、いつしか水は両手からこぼれ落ちる”
解ったつもりでいて、永遠にわからない。
理解できない藪の中の曖昧模糊。
そうやって、説明をはぐらかします(ズルイですけど)
だから世界が小津を敬愛し、作品を何度も見返し、魅了する。
そう思います。
<2.楽しい酒の酌み交わしかた>
小津さんは、エッセイで「映画の中の酒のシーン」について、こう書いている。
“映画の中での酒のシーンは多々あるけれど、私が一番撮って好きなのは、小料理屋で気分の合った仲間が、静かに体を乱さず、適量の徳利を前にして飲み、かつ談ずるところがいい。
私自身がそんな飲み方をするからではなく、見ていて、それが一番楽しそうだからである。“
僕も激しく同意します。
年配の諸先輩が小料理屋で、そんな飲み方をしていると、惚れ惚れする。
死ぬまでにあと何回、うまい酒を酌み交わすことができるか。
そんな境地の酒飲みには、まだまだ達することができませんが。
<3.戦争を語らない退役軍人の監督>
小津監督は先の大戦で2度従軍している。
松竹映画で新進気鋭の監督としてのキャリアを有しながらも、1937年9月に33歳の小津監督は、下級兵士として中国戦線で2年間も兵隊生活を送っている。
戦場で多くの映画人の友をなくしている。
肌身離さずに携帯していたライカのカメラで何を写しのか、何を思ったのか、後に何も語っていない。
そして、2度目は1942年に陸軍報道部映画班として従軍し、シンガポールで敗戦を迎え、半年間の捕虜生活を経験している。
30代から40代前半の長き時間を戦場で暮らしながら、戦後はその体験を語らず、作品中でも一貫して戦場を描いていない。
しかし、戦場の善悪を介すわけでもなく、戦争の影を小さなシーンに織り交ぜている作品は多い(「東京物語」では戦死した次男の遺影について触れている)。
それは厭世的でもなく、あるがままの敗戦を受け入れ、暮らしの日常の戦後を描いている。
徴兵を逃れた黒澤明監督が戦後を描けず、近代以前の楽観的なヒロイズムしか追えなかったことと大違いである。
戦場の生と死の狭間に身を置いた経験のある直感とリアリズム、そこから「必要」と「不必要」を仕分け、純化した映画の結晶を削り仕立てる。
偉丈夫の映画監督『小津安二郎』の作品について、理解する丹念は到底に得ることはできません。
しかし、そこが魅力なんです。
それでは、また来週まで。
おやすみなさい。